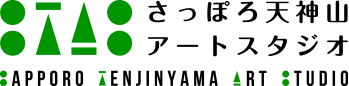2016年08月26日 イベント創作活動滞在者紹介
8月25日よりJunichiこと大勝 純一さんが滞在中。着いて早々に作業にとりかかっているJunichiさん、9月2日まで制作展示を行います。

今回は10月の名古屋長者町トランジットビル内ギャラリーカプセルでの展示、11月の東京は京橋Keyギャラリーでの展示に向けた制作を兼ねているとのことです。
また、あいちトリエンナーレに関連したこちらの企画「都市木」にも出品が決まっています。http://toshimokugallery.com/
名古屋ではSTORE ROOMにてイム•ヨナスさんとの共同企画を展示中。こちらは9月11日まで開催です。
名古屋を拠点に活動されているJunichiさんですが、出身は札幌だそうです。会期終盤が見頃になるそうなので、ゆかりの方など、お越しいただければと思います。
From 8/25 an artist Jyunichi stays in Tenjin. As soon he began working. He is going to hold work in progress exhibition until 9/2. This time is also as working for exhibition at Gallery Capcel and anothe exhibition at Key Gallery in Tokyo.
He also will exhibit in the project Toshimoku「都市木」which related to Aichi Triennale. http://toshimokugallery.com/ And now he holds exhibition at STORE ROOM with a Korean artist until 9/11.
His activity based on Nagoya now, but was born in Sapporo. He told that this exhibition will be completed gradually for 9/2.
taiga.
2016年08月26日 日常滞在アーティストと市民の交流企画
さっぽろ天神山アートスタジオ 滞在アーティストと市民の交流企画
『能楽を見に行く』
先日、滞在アーティストと共に近隣小学校に「能楽」を見に行ってきました。

参加アーティストは4名。
ダネ/カンボジア、マリーナ/台湾、ティム&ジャスティン/オーストラリアです。
演目はふたつ。
狂言の「柿山伏」と能の「羽衣」

演目中の写真撮影は禁止との事で、その様子は写真に撮りませんでしたが、
人生で初めての能を楽しんでいたようです。
そして、能の見学だけでなく、小学校の中も探索。

理科室、音楽室、図工室、コンピューター室など、
彼らは日本の小学校に入るのは初めてで、興味津々の様子。
そして、飛び入りでお邪魔した小学校のクラス訪問

お邪魔したのは1年生のクラス。
各アーティストには各々の言語で自己紹介をしてもらいました。

初めて聞く、台湾語、カンボジア語に子ども達も興味津々。
また、生の英語にも子ども達は釘づけでした。
こういった日常風景を見られる機会はあまりないため、
参加したアーティストも満足してくれたみたいです。
こんな感じで、天神山のアーティストと市民の交流をどんどん生み出してゆきますよ!
「私も参加したい!」「ぜひ、来てほしい!」という方は
遠慮せずに、下記の連絡先までお願いいたします。
さっぽろ天神山アートスタジオ 滞在アーティストと市民の交流企画
『能楽を見に行く』
8月23日(火) 10:30~12:30 平岸高台小学校(豊平区)
◆滞在アーティストと市民の交流企画とは◆
さっぽろ天神山アートスタジオに滞在するアーティストと市民の交流を促進するため
アーティストが天神山を飛び出し地域や人に会いに行ったり、
市民がアーティストやアーティストの活動場所に積極的に出向いてゆく企画です。
担当: 小林亮太郎 連絡先: ryotaro@ais-p.jp 070-5288-5367
2016年08月25日 滞在アーティストと市民の交流企画
日曜日の撮影会では天神山に滞在中のアーティストにインタビューを行ったMarina、日本の法制度や犯罪心理に関してより専門性の高いものを取材したいということで、この日は弁護士でSalon Cojicaのオーナーである川上大雅さんにお越しいただきました。
まずは天神山麓にある喫茶店ブロンディにて昼食。カメラを向けると笑ってくれましたが、死刑制度についての考え方や、川上さんが過去に弁護を担当した殺人事件、医療診断と法廷の関わりなど、会話の内容は非常にシリアスなものが続きました。

天神山に戻って改めての収録。トータルで3時間近くに及ぶ取材を終えた川上さん「すごく色々なことを考えさせられましたが、普段仕事の中では考えられないことを改めて振り返るよい機会になりました」とのことでした。
Marinaはいつもは気がねない雰囲気ですが、カメラを構えると険しい表情。こんなことを言っていました。「元々の私はピュアでこんな風じゃないけど、映画に全てを注いできて、そしてディレクターになるために性格もどんどん変わっていったわ。それが生きてるってことよね」

At last Sunday, Marina held an interview event and she took artists in Tenjin. So she needs some higher specialties for interviewee like Japanese legal system or criminal psychology, this day we invited Taiga Kawakami. He is not only a lawyer, but also owner of the art gallery Salon Cojica.
At first they had a lunch at cafe Brondy in foot of Tenjin. Though they smiled for camera, they were talking about very serious themes such like the way of thinking of death penalty, a murder case that he carried, relation between doctor opinion and court and so on.
Taking interview in Tenjin. After 3 hours meeting he said “I had to consider a lot, but it was good opportunity to look back things that I can’t consider enough in daily work.
Meanwhile, Marina in camera work looks serious not as usual. She said like “I was not like this before. But I has been spending all of me to make film. For being as a film director, I was changing even my personality. That’s life right? ”
taiga.
2016年08月24日 イベント滞在アーティストと市民の交流企画
8月21日、ドキュメンタリー映画監督Marinaによる製作中の作品の一部上映会とそれに続くインタビュー撮影が行われました。
数年前に台湾で起きたある無差別殺人事件を追いながら、未成年犯罪とそれに対するアートの働きかけをテーマにドキュメンタリーを製作中のMarinaは、現在までにポルトガル、ロンドン、九州でインタビューを収め、今回の天神山での撮影に臨んでいました。イベント前半では各地での収録を上映し、参加者はそのインタビューから、ポルトガルのミュージシャンらの音楽による社会への働きかけやその考え方、ロンドン、あるいはポルトガルのスラムの少年らによるこの事件への意見を聞きました。


台湾で大きな波紋を呼んだこの事件。加害者の青年が映画「バトル ロワイヤル」の原作小説に影響を受けていたことを供述しており、Marinaは日本でのロケを敢行する理由として挙げています。
約30分の上映会後に参加者へのインタビュー撮影へと移行し、滞在中のアーティストを中心に、さまざまな意見がMarinaのカメラへと収まっていきました。
ある日の彼女の言葉です。 「アートが犯罪に対して有効であるということや、この社会をいかに良くしているかを証明すること。それはとても難しいことだけど、このドキュメンタリーを通じてそれに挑戦しているのよ」


An report of the event by documentary filmmaker Marina. This event had two parts, screening of her processing work and interview.
Following an indiscriminate murder in Taiwan few years ago, Marina has been focusing crimes of young generation and what the art can work to them. So far she has took interviews in Portugal, London and Kyushu in Japan then she was going to hold this screening & interview event at Tenjin. In screening we saw the interviews that have been took in those places. The participants could hear that opinions of Portugal musicians that how they act to the society and their way of thinking, and that opinions of boys in London or slam in Portugal for this case.
This murder case brought about big problem in Taiwan. Marina mentions that the young murderer revealed that he was influenced from a Japanese novel “Battle Royal” as a reason why she choses Japan to film. This novel is known more as its cinema. After about 30 minutes screening, Marina took interview. Lots of various opinions might be took into her camera.
One day she said. “To prove that the art is available to crime or how it makes the society well. It is very difficult, but I am challenging through making this documentary film”
taiga.
2016年08月23日 滞在アーティストと市民の交流企画
8月のArt&Breakfast、食卓にはサルサソースの蒸し鶏や肉巻き、黄色のスイカなどなど、目にも鮮やかなお料理が並びました。天神山からはオフィス横の小さな畑に茂ったバジルでジェノベーゼソースのパスタを。ボーノボーノ。

アーティストトークはオーストラリアのミュージシャン、自身が演じる映像もマルチにこなすSui Zhen(スー チェン)ことBeckyが担当。Sui Zhenはマレーシアの血を引くBeckyの中国語名。彼女はそこからSusan(スーザン)という仮想のキャラクターを作り、映像作品まで一貫した演出をすることで、インターネット社会でのアイデンティティの流動性や、80年代90年代の典型的なイメージを現代の自分が再現(いわゆるシュミラクル)することで生まれる違和感を示し、それを作品の構成要素としています。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLt17xfGWC3wvB8NYUXSiu4p7o5wNylE2
最新作「こっそりスーザン」は本国オーストラリアではLPレコードで発売中。日本でも9月にCDが発売されます。また、8月27日には札幌のラウンジ、PROVOのイベントに参加するとのことです。

At the event Art & Breakfast Day in Tenjin in August. Steamed Chicken with Salsa source, Polk roll and yellow water melon and so on, there were many splendid dishes on the table. From Tenjin, Spagetti Genova source made from basils of the tiny farm by the office. Buono Buono.
The artist talk was by an Australian musician Becky a.k.a Sui Zhen. who is multidisciplinary artist. She acts and edit by herself in her music video works. A part of her name Sui Zhen is from her Malaysian mother. Through making imaginal character Susan, she implies fluidity identity in recent internet society, and express so called “uncanny valley” from replicated typical image of 80’s and 90’s by the present herself. Her works consist from those concepts like simulacra.
The new piece “Secret Susan” has already came out in Australia as LP record. And also in Japan, CD version will be published on coming September. On 8/27 she is going to act at the lounge event at PROVO in Sapporo.
taiga.
2016年08月20日 滞在者紹介
3331アーツ千代田より、吉倉千尋さんがやってきました。
吉倉さんはレジデンス担当として、日本各地のレジデンスを回っており、
今回も天神山アートスタジオや周辺環境のリサーチのために来館。
8/21のアート&ブレックファストデーにも参加するとの事。
たまたま、天神山に来ていた地域サポーターの川島さんにも、色々と質問をしていました。

2016年08月20日 滞在者紹介
兵庫の画家、山本法子さんが滞在中です。


山本さん、現在札幌での展覧会「サッポロ未来展」に出品中です。詳細は下記のリンクをご参照ください。
第15回記念 サッポロ未来展ホームページ
http://www.sapporomiraiten.com/
第15回記念 サッポロ未来展Facebook
https://www.facebook.com/sapporomiraiten/
A painter Noriko Yamamoto stays Tenjin. She is one participants of the exhibition. Here is links of the event.
http://www.sapporomiraiten.com/
https://www.facebook.com/sapporomiraiten/
taiga.
2016年08月20日 滞在者紹介
オーストラリアのJustineとTim、文筆家の二人が滞在中です。

Timはフィクション作家で、現在はヤングアダルト向けの三部作を執筆中。テーマを聞くと「世界の終わり、この文明の終わりの話だ」とのこと。さらに、悲観的、楽観的、どんな見地から書いているか尋ねてみましたが、それはさすがに瞬時に答えるのは難しい様子。そんなあなたに、ということで、たまたまオフィスにあったナウシカの原作コミックと英語の要約を渡してみました。
Justineの執筆はTimによればよりアカデミックで、大学で現代のパフォーミングアーツ理論を教えているとのことです。
二人は10/17までの長期滞在です。
Justine and Tim, Australian writer couple stay in Tenjin. Tim is a fiction writer and is writing a trilogy for young adults now. “The end of this world. The end of this civilization.” He answered about the theme of them. Then I asked more that from what viewpoint is written. But he seemed hard to answer immediately. I rent the original comics of “Nausica of the valley of the wind” and its English summary, so there were in the office coincidently.
According to Tim’s word, Justine’s works are more academic. In an university she teaches theory of contemporary performing arts apparently.
Their long visit is until 10/17.
taiga.
2016年08月17日 滞在者紹介
オフィスにいるこの男・・・
ご存知でしょうか?

2014年度冬のバカンス招聘アーティストのウェン・ナム・ヤプがやってきました。
⇒ HP
⇒ 冬のバカンス

マレーシア出身のアーティスト、ウェン・ナム・ヤプ。
彼は8月20日(土)~9月10日(土)の間、
是非、皆さんもウェンナムに会いに来てください!
2016年08月16日 イベント日常滞在者紹介
さっぽろ天神山アートスタジオ 滞在アーティストと市民の交流企画
『鈴木悠哉小学校へ行く』

7月14日(木) 10時~15時 平岸高台小学校(豊平区)
内容 作品・活動紹介、児童との交流
◆滞在アーティストと市民の交流企画とは◆
さっぽろ天神山アートスタジオに滞在するアーティストと市民の交流を促進するため
アーティストが天神山を飛び出し地域や人に会いに行ったり、
市民がアーティストやアーティストの活動場所に積極的に出向いてゆく企画です。
担当: 小林亮太郎 連絡先: ryotaro@ais-p.jp 070-5288-5367
さっぽろ天神山アートスタジオによる「滞在アーティストと市民の交流企画」として
滞在アーテイストの鈴木悠哉さんが平岸高台小学校に訪れました。
中休み、昼休み時間に作品や活動の紹介を行いながら子ども達との交流を深めました。
その時の様子をブログでご紹介いたします。
(当交流活動は2016年7月14日に行われました)
・自己紹介&作品紹介の様子

・今まで見たことのない世界にたくさんの質問や意見が飛び交う

交流企画を実施後、鈴木悠哉さんから感想を伺いました。
「学校」という言葉を聞いて、なんとなく楽しいイメージを抱く子供と、なんとなくいやだなあ、
と感じる子供とだいたい2種類に分かれると思うが、自分は一貫して後者であった気がする。
今回20数年ぶりに小学校(平岸高台小学校)を訪問することになった。実際に行ってみると、
学校は自分の記憶のなかの学校のイメージとはだいぶかけ離れていた。
学校は、明るく、オープンな雰囲気に満ちていた。こどもが生き生きしている。
廊下を走り回っている。というより、廊下で運動ができるように運動マットも敷いてある。
中休みと昼休みの時間利用して、自分の作品や、今まで行った国の写真などでプレゼンテーションを行う。
果たして、自分がこどものときに、学校の中にこういうよくわからない時間があって、
よくわからない大人が来たらなにを思っただろうか。学校の授業はたいがい答えが決まっているし、
正しい答えを導き出すために知識を覚えている。だけど、このよくわからない時間はやはりよくわからないままだ。
だが、この世界に「よくわからないことがある」ということを許容することはとても大事なことなんじゃないだろうか。
(>とくに美術はその部分に大きく関わることだと考える)
学校のなかの様子も見せていただいた。時代は変わり、少子化は進んでいた。一学年は一クラスになっていた。
だが、そのことで先生と生徒の距離は縮まり、また生徒たち同士も親密なように見えた。
正直、この情報化社会の現代において、子供達の日常も昔ほど牧歌的なものではなくなっているのではないかと
推測していたが、そんな心配をよそに、一見したところ子供達はのびのびしている印象だった。
※平岸高台小学校は1年2年以外は1クラス学級。
・写真を見ながらこれまで訪れた様々な国の話をする鈴木さん

個人的に、一番驚いたのは校長先生だった。イメージのなかの校長とまったく違う。
話を聞くと、となりの特別支援学校などでも校長を兼任しているそうで、そういうマイノリティの視点から
ものを考える姿勢がうかがえる。(そもそも校長先生自身が学校嫌いだったそうだし。)
校長先生はひとまずえらい、という理由なき威厳みたいなものがひとかけらもない。
これはこの学校のほかの先生にも言えることだった。
先生はえらい、だからいう事を聞かないといけないという頭ごなしの教育スタイルがここにはみあたらない。
きちんと人間と人間の関係が先生と生徒のあいだにある気がした。
(もちろん、内情は様々な問題を抱えているとは思うし、その苦労を推し量ることはできないにしても)
※池田校長は「平岸高台小学校」と「のぞみ分校」の両校の校長を兼任している/2016年7/14現在
あと、校長先生のほうから(自分の作品のイメージを使っての)提案があったのも驚いた。
個人的にこういったオープンさ、自分たちにプラスになるものを積極的に受け入れる姿勢は
ヨーロッパの教育の感じに近い印象を受けた。
たしかに美術を取り入れた企画がこの学校では実現しやすいと感じる。
・様々な学年の子供たちが集まってくる

子供に関しても少人数制ということもあるのか、あぶれている生徒がいる感じがしない。
自分の小学校のときは1クラス40人、5クラスの大人数だったために、必ず孤立する生徒が居たものだった。
少なからずクラスに派閥が形成され、
子供ながらにその社交関係や権力のヒエラルキーのようなものが嫌いだった。
1クラスしかないので、クラスわけで人が入れ替わることがないというのは、
総じて良いことなのかもしれないと感じた。(まあ、これも一長一短だと思う)
あと、また個人的に衝撃だったのは英語の授業。軽く嫉妬を覚える。
授業はヒアリングとスピーキング重視のもの。中、高と英語を暗記科目として捉えていたために、
大人になって日本から出た時に苦労したし、いまも苦労し続けている。
こどものうちから学校で生の英語に触れるということはかなり重要な体験だと思う。
※ALT(外国語指導助手/ネイティブスピーカー)による会話の授業を見学した。
プレゼンは20分、20分の2回。※中休み、昼休み
なにを見せるかのプランは少しはあったにしても、プランを立ててもこどもの前では速攻覆されるのだな、
ということを悟る。逆にそれが面白さなのかもしれない。偶然性や即興性しかないのだと。
(鈴木悠哉/現代美術)
~企画を実施して~
今回、小学校への交流企画を実施したことで、
子ども達はアーティストに出会い、作品や活動の紹介を通じて
ものの見方や考え方、そしてこんな生き方もあるんだ、という体験をした。
また、参加したアーティストも小学校を訪れることで、今の小学校の姿や
子ども達・先生達に触れ、過去の経験を更新する機会になったのだと思う。
さっぽろ天神山アートスタジオでは、館内での交流事業はもちろんのこと
これからも出会いから生まれる、驚き、喜び、楽しみ、を積極的に作ってゆきたいと考えている。
さっぽろ天神山アートスタジオ 小林亮太郎